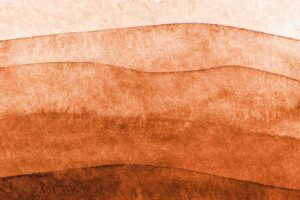・上の子がかわいくない症候群とは
・上の子がかわいくない理由
・上の子がかわいくないと感じる裏にあるもの
かわいくない上の子に冷たくしがち、でもかわいい下の子はつい甘やかしてしまう
そしてそんな自分に罪悪感・・・
これって上の子かわいくない症候群???
ここではそんな風に感じている方の心を少しでも軽くするために、上の子がかわいくないと感じる理由や対処法などをお伝えしたいと思います。
上の子かわいくない症候群とは
『上の子かわいくない症候群』は『症候群』と名前がついていますが、医師が診断の際使うような病名ではありません。
一般的には、下の子が生まれ、上の子がかわいいと思えなくなる状態、を『上の子がかわいくない症候群』と呼びます。
でもこういう病名のような名前がつくということは、世の中に「上の子がかわいくない」と感じ、そのことについて悩む親がとても多いということだと思います。
肉体の症状をイメージしてください。
なんだか疲れやすい、息切れする、ふらつく・・・ なんなんだろう・・・
そんな時に、「あなたは貧血ですね」と診断されたらちょっと安心しますよね。
そんな感じです。
大丈夫、『上の子かわいくない症候群』に悩む母親はあなただけではありません。
上の子がかわいくないと感じる母親は、ダメな母親なのか?
いいえ!
下の子のように上の子をかわいいと思えない、と悩んで、こうやって記事を読んでいると言うことは、かわいくないと思う上の子どもが気になっているということです。
愛の反対は無関心。
上の子を本当に愛していないのなら、上の子の存在自体に無関心になっているはずです。
自分ってダメな母親かも・・・と罪悪感を抱き悩み、こうやって記事を読むくらいなのですから、かなりの時間とエネルギーと関心を、上の子どもに向けているはず。
それは充分、上の子のことを愛していると言えると思います。
でもね、上の子どものことを本当は気にかけていて、それが愛情と呼べるものだとしても、子どもに愛情として伝わらないのは勿体無い。
子どもにとってはわかりやすくかわいがってもらえた方が、愛情として受け取りやすいし、明らかに自分よりもかわいがってもらっているように見える他の子どもと比べて自己否定感を抱きがちでしょう。
子どもの自己否定感は、親に対し反抗的だったり、いじけやすねなどの問題行動として、表面化するように思います。
すると、ますます親にとってはかわいくない子どもになっていく悪循環が生じてきます。
そんな悪循環を解消していきたいですよね。
さて次からは、どうして上の子に対してかわいくないと感じてしまいやすいのか理由を探っていきたいと思います。
上の子がかわいくない理由

かわいいと思う下の子ども、かわいいと思えない上の子ども、違いは一体なんなのでしょうか?
まずかわいいと感じる下の子どもに対し感じるのはポジティブな気持ちでしょう。
「気持ち良くなる」「嬉しくなる」「楽しくなる」「安心する」「心地いい」「フワッとする」などなど・・・
反面、かわいくない感じる上の子どもに対して感じるのは、ネガティブ、つまり嫌な気持ちだと思います。
「イライラする」「不安になる」「心配になる」「悲しくなる」「怖くなる」「もやもやする」などなど・・・
人はいい気持ちにさせてくれる人に対し優しくしたいし、一緒にいたいと思いがちです。
反対に、嫌な気持ちにさせる人とはかわいいというようなポジティブな気持ちになれないし一緒にいたいとは思わない。
自分を嫌な気持ちにさせる人なんだから、そっけなくしたり、冷たく扱ったり、相手が嫌な気持ちになるようなことをしてもいいだろう、と思ってしまうでしょう。
同じ自分の子どもなのに、上の子、下の子、気持ちの差が出るのは、子どもたちが自分をいい気持ちにさせる存在なのか、嫌な気持ちにさせる存在なのか、の違いがあるからです。
どうして子どもによって感じる気持ちが変わるのか?

ではどうして子どもによって、感じる気持ちに差が出てしまうのでしょうか。
真っ当な親なら子どもを平等に同じようにかわいいと思えるものなのではないでしょうか。
いえ、親だって、子どもだって、個性のある人間です。
相性だってあります。
普通に世間に出て、仲良くなる人もいれば、ピリピリ感が漂う関係性の人もいるようなことと同じです。
でも、そうやって割り切って、気持ちに余裕ができるならいいと思います。
気持ちに余裕ができると、かわいくないと感じる上の子どもへの態度や行動も、少し穏やかなものになる可能性が高いからです。
ただ、そう簡単に割り切れるものでもないですよね。
せっかく生まれてきてくれた我が子、できればみんなと楽しく過ごしたいと願う気持ちが大きいからこそ悩むのだと思います。
また『上の子かわいくない症候群』という言葉ができるほど、上の子にかわいくないと感じる人は一定数おり、相性だけのせいとは言いきれなさそうです。
では次にどうして上の子はかわいくないと感じやすいのか、3つの理由を探っていきましょう。
上の子がかわいくないと感じる 4つの理由
① なにもかもが初めてだから
最初に生まれてきてくれた子どもは子育てのなにもかもが初めての子どもです。
何があってるのか間違っているのかわからない不安の中を責任感を感じながら、進んでいかなくてはなりません。
また上の子どもは、小さい頃は体重の増え方・オムツが外れる時期など、大きくなれば成績や習い事など、統計や他の子どもと比べてしまい、これでいいのかと落ち込んだりもしがちです。
初めての子育ては自分に対しても子どもに対してもやたらと期待を大きく持ってしまいがちのため、思い通りにいかないことも多いでしょう。
なので上の子の子育ては心配や不安、焦りなどで心の余裕がなくなりがちです。
心の余裕がなくなると、その原因となる上の子に対してかわいいと思えなくなります。
反面、2番目以降の子どもの子育ては一番上の子の経験があるので、子どもってこんなものだよねと安心しやすく、それほど期待を持たずにすみ、余裕をもっていられます。
余裕があるとポジティブな気持ちをいだきやすく、上の子に比べて下の子は、かわいいな、一緒にいると楽しいな、と感じることも多くなります。
② 姿形が下の子に比べてかわいくないから
子どもは幼ければ幼いほど、その姿形をかわいいと感じるものです。
かわいいと感じる赤ちゃんや幼い子どもは以下のような特徴を持っています。
頭が大きい、顔全体からすると目の割合が大きい、黒目の部分が多く丸い目をしている、鼻と口が小さく頬がふくらんでいる、体がずんぐりふっくらしている
これらの特徴をベビーシェマといいます。
無力な存在である赤ちゃんや幼児は大人から保護される必要があります。
なので、人間の種を存続させる本能として、ベビーシェマを持つ子どもをかわいいと感じ、自然とお世話をしたくなるのです。
子どもは成長するにつれて、丸っこい印象から、どんどん縦長に変化していきます。
顔が大きくなり、顔のパーツも中心に寄っていたのがそれぞれ離れていって、小さい頃の小動物のようなかわいさからは遠のいていきます。
下の子は上の子よりまだベビーシューマを感じさせる部分が残っています(年齢にもよりますが)。
なので上の子は下の子に比べてかわいいと感じないというのは、人の本能として当然のことなのです。
③ 年上としての振る舞いを求めてしまうから
上の子は下の子に比べて、できることも多く、自制もききます。
なので自然と、上の子にはしっかりとしてほしい、下の子に優しくしてほしい、親の手を借りずに一人でやってほしい、下の子の面倒をみてほしい、などと期待値が大きくなります。
でも、下の子よりはやれることが多くてしっかりしているように見えても、まだまだ子ども。
期待に応えられない時も多々あるでしょう。
でも期待した役割を果たしてくれない時は、がっかりして裏切られた気分になりがちです。
特に余裕がない時はそうですね。
なので頻繁に自分の期待を裏切る上の子に対し、かわいくないと感じやすくなります。
④ 下の子は上の子に比べて愛され上手だから
下の子が生まれるまで親の注目を一身に集めていた上の子。
しかし下の子は違います。
上の子と親の注目を奪い合わなければなりません。
なので、上の子と親をよく観察し、上の子が親とうまくいかなくなるパターンを無意識に学びます。
そして、無邪気に甘えたりするなど、親に気に入られるパターンを身につけていきます。
当たり前のように親の注目を集めていた上の子は、そこまで気が回らないことがほとんどです。
また上の子は、かわいさ勝負で下の子に勝てないならと、わざと親を困らせることをして、親の注目を集めようともしてしまいます。
愛され上手の下の子、どこか不器用な上の子、そりゃ、上の子はかわいくない!ってなってしまいますよね。
上の子がかわいくない、解決策は?
上の子がかわいくない、と悩む時は、以下の3つのことを試してみましょう。
① 上の子と二人で過ごす時間をとる
下の子と一緒だと、余裕がなくなり、どうしても上の子に年上の役割を求めてしまったり、下の子とかわいさを比べてしまったりします。
なので、週に1回くらいは下の子を配偶者や親、一時保育やシッターに預けるなどして、上の子と二人きりの落ち着いた時間をとるとよいでしょう。
上の子も母親の注目が自分に注がれるので、精神的に安定し素直になりやすいです。
すると、かわいいという気持ちが湧いてきやすかったりします。
② 上の子が小さかった頃の姿を思い出す
下の子と比べると、上の子は大きくてかわいくない子どもに思えてしまいますが、上の子も下の子のようなベビーシェマたっぷりの時代がありました。
上の子の小さい頃の写真や動画などをみて、当時の気持ちを思い出してみましょう。
また今はかわいい下の子も上の子の年齢になる時がきます。
上の子と下の子の年齢が逆転したらどうなっていたか、想像してみるのもいいでしょう。
上の子がかわいくないという気持ちがちょっと客観視できるかもしれません。
③ 上の子にポジティブな声かけをたくさんする
かわいくないと感じると、つい日常的な言葉かけもネガティブな厳しいものになってしまいがちです。
「ちゃんとして!」
「もー、がっかりさせないでよ」
「お姉ちゃん(お兄ちゃん)なんだからね」
などなど
言葉にはエネルギーがあります。
水の結晶の話をご存知でしょうか。
ポジティブな言葉をかけ続けた水から生まれる結晶はとても綺麗な形をしています。
ネガティブな言葉をかけ続けた水からできた結晶は、つぶれたり壊れたりして、ゆがんだ形をしています。
子どもの体の約70%が水分と言われています。
上の子どもの中に、きれいな水の結晶がたくさんできるイメージで、ポジティブな言葉かけをたくさんしてあげましょう。
「かわいいね」
「大好きだよ」
「すごいね!」
などなど・・・
心からそう思えなくても大丈夫。
言っているうちに、本当にそう思えてきたりします。
ポジティブな言葉を言っている自分の体の水にもいい効果があるからでしょう。
かわいくない上の子どもが教えてくれること
時には、(この子さえいなければ私は安定していられるのに)とまで考えてしまう、かわいくない上の子ども。
実は、かわいくないと感じる上の子どもは親に大事なことを教えてくれる存在なのです。
では大事なこととは一体なんでしょうか。
・もっと自分を大事にした方がよいこと

余裕がなくなると人はポジティブな気持ちを感じにくくなります。
もし子育てや家事、仕事やお金、夫婦関係や人間関係のストレスから全て解放されたとしたら、どんな感覚になると思いますか?
色々と些細なことはどうでもよくなって、おおらかな自由なすっきりした気分なる自分が想像できるのではないでしょうか?
上の子がかわいくない、と悩むあなたは、自分で感じる以上に相当のストレスにさらされているはずです。
そのままの生活を続けても、さらにストレスをさらされ、上の子どもとの関係性も悪循環になっていく可能性が高いです。
なので、まずはご自身のストレスを減らし、心の余裕を生み出しましょう。
そこでストレスを減らし、心の余裕を生み出すためには、ご自身を大事にするということをやってみてください。
自分を大事にするってどんなことが思い浮かびますか?
まずは些細なことから、自分を大事にすることをしてみましょう。
・自分に花のプレゼントをする
・ゆっくりお風呂に入る
・家事を全部放棄して寝る
・行きたかったカフェで一人でゆっくりする
・丁寧にストレッチする、 などなど・・・
いきなり、一人旅に出る!とかは難しいかもしれませんが、些細なことから自分を大事にする選択を積み上げていけば、心の余裕が少しずつでてきます。
するとかわいくないと感じる上の子どもとの距離感も少しずつ、心地いいものに調整されてくると思います。
・あなたの中に心の傷=インナーチャイルド=があるということ

実はあなたが自分のことを嫌いであればあるだけ、上の子の中に自分の嫌いな部分を見出し嫌な気持ちになります。
そしてそんな気持ちにさせる上の子はかわいくないと感じるのです。
どうしてあなたは自分のことを嫌いになってしまったのでしょうか。
それはあなたの子どもの頃の親との関係にヒントがあります。
例えば、あなたが子どもの頃、言い訳をすると親から叱られていたとします。
このことが心の傷になると、親に言い訳をする自分はダメな子であり、親から嫌われる自分なので、自分でもそんな自分を嫌いになっていきます。
何度か同じようなことが繰り返されると、心の傷は深くなり、インナーチャイルドとなって心の奥底に残るようになります。
そしてそんなことも忘れて大人になって、子どもが産まれ、上の子どもがあの頃の自分と同じように言い訳している姿を見た時に、心の奥底にあるインナーチャイルドが刺激されます。
そして当時の嫌な気持ちが無意識によみがえり、いろんな感情が湧いてきて、心が揺れるのです。
またインナーチャイルドが大きければ大きいほど、ありのままの自分や相手を認められないため、自分に対しての期待も相手に対しての期待も大きくなる傾向にあります。
相手が子どもの場合、期待が大きいほど、裏切られることも多く、嫌な気持ちになることも多いのです。
またインナーチャイルドが大きくありのままの自分や相手を認められない状態だと、心からリラックスすることは難しくストレスを抱えがちになります。
かわいくないと感じる上の子どもはあなたにインナーチャイルドがあることを教えてくれているのです。
上の子どもの中に自分の小さい頃を思い出し、嫌な気持ちになることはないですか?
そういった記憶と同時の想いや感情を思い返すことで、インナーチャイルドが癒される場合もあります。
インナーチャイルドは心の奥底にあってなかなか扱うのは難しいですが、適切に扱って癒すことができると、人生が変わるような経験をすることができます。
ご自身のインナーチャイルドが気になる方で一人で扱うにはどうしたらいいかよくわからない時は、専門家に相談されてみるのもよいと思います。
私自身は2009年からインナーチャイルドを取り扱うセッションを提供しています。
自然な変化をサポートする、なかなか面白いセッションですので興味がある方はこちらのページをご覧ください。
まとめ

私は12年以上、子育てに悩む方にセッションを提供してきています。
その方々の変化を目にしてきて実感するのが、子どもっていろんなことを親に教えてくれてるんだということ。
それをちゃんと受け取って、自分を変えることに活かしていけば、子どもとの関係は驚くほど変わっていきます。
かわいくないと感じていた上の子どもが、唯一無二の人生の親友、みたいな存在になったりもします。
ああ、子どもって、親をサポートするために生まれてくるんだな、と思うこともよくあります。
あなたの子育てが人生が、心から楽しめるものになっていくように応援しています。
またご質問や気になることなどがあれば、私のホームページからいつでもご質問ください。
『子育てのイライラをエネルギーで扱おう!』PDF本プレゼント中 詳しくは画像をクリック!
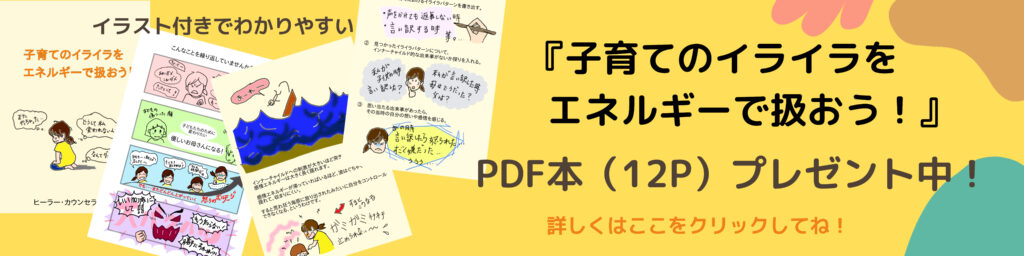
関連記事