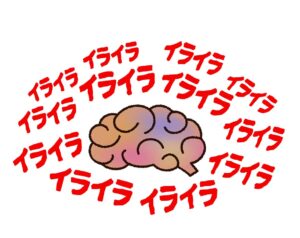- 子どもの不安を和らげ、喜ばれる親の4つの行動
- うるさい、ウザい親の特徴・ワースト3
- 親ができる究極の在り方
子どもの卒業と就職が決まり、社会に巣立てば、親も子育て卒業です。
生まれてから、這えば立て、立てば歩めと、叱咤激励して育ててきましたね。
最後だからこそ、就活にも口出しをしてしまうのかもしれません。
ですが、相手も大人です。
今までと同じ関わり方だと険悪なムードになってしまいます。
就活生の9割は不安の中にいる

株式会社デジタル・ナレッジ「大学生の就職活動に関する意識調査報告書」(2016.6.27発表)から就活学生の87%が就職や就活に不安を感じていることがわかります。
不安を感じながらも相談する相手は、プロではなく身近な人か誰にも相談していないという結果が出ています。
子どもは不安を誰に相談するのか
悩みを相談する相手は
- 同年代の親しい友人(過半数)
- 家族
- 大学の先輩
と続き、
20数パーセントの学生は誰にも相談していないという結果が出ています。
就活自体が戦略やテクニックが必要なものになっているのに、就活支援の専門家にではなく、友人・先輩や家族といった身近な人に相談しています。
身近な人に相談するメリット
一番のメリットは、自分のしんどさ、つらさをわかってもらえた!と思えること。
悩みを抱えているのが自分一人ではないと思えたり、共感や承認が得られるとホッとします。
例えば、友人だと「お前も大変だな、俺もさ、頑張るから、お前も頑張ろう」という励ましがやる気や意欲につながりますね。
相手に成功体験があれば今後の参考にもなります。
身近な人に相談するデメリット
デメリットは、相談相手によっては、自分が取り残される焦燥感や孤独感、さらなる不安に陥ることがあります。
不安が高じて怒りへと発展することもあります。
これは、相談相手と自分との間にギャップを感じた時に起こりやすいです。
例えば「友人は上手くいっているのに自分は…」と落ち込んでしまいます。
また、相談相手が就活支援の専門家でないので、情報量や客観性が不十分で適切な状況分析が難しくなります。
親子関係では、親の在り方によってこれらのデメリットの方が大きく出る傾向にあります。
就活の手助けをしているつもりが、逆に「ウザい、うるさい親」になってしまう原因です。
親世代とは違う今時の就活環境
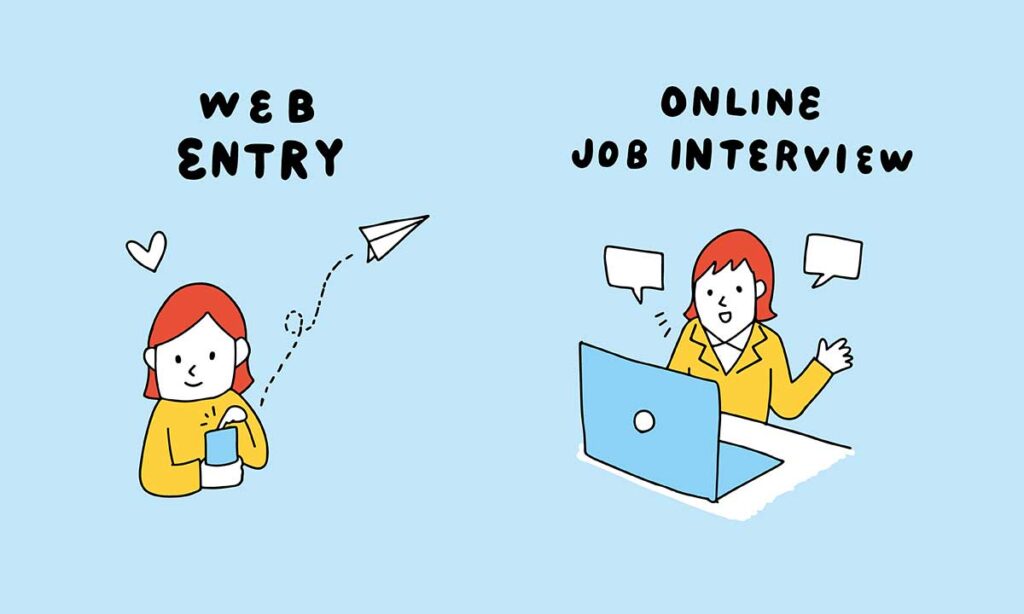
頭を切り替えましょう!
今時の就活は、自分たちの時代とは全く違います。
あの頃は、時代はアナログ。
求人票も企業情報も紙ベースでした。
「エントリー」や「インターンシップ」といった専門用語もありませんでした。
子どもたちは、デジタル社会で情報があふれる中を奮闘しているのです。
- 日本の終身雇用、年功序列はもはや当てにならない
- 倍率が高すぎて、不採用連発は当たり前
- 就活は大学3年の春から長期戦
- 戦略、テクニックなどスキルを習得した者が断然強い
- ネット利用でエントリーしやすく、応募数が膨れ上がる
- インターンシップ(就労体験)がある
- 時間/労力/お金がかかる
- 日本人だけじゃなく、外国人留学生も超ライバル
このほか、自己分析や企業研究、企業へのPRなど、学業よりも就活に時間が取られる有様です。
いやはや、親が思っている以上に大変です。
子ども自身、就活は初めてです。
受験よりもずっと戸惑っているだろうし、どうしてよいかわからないこともたくさんあります。
試行錯誤する中で、うまくいく人をうらやんだり、やってもやっても結果が出ない自分に凹んだり。
もがいて壁にぶち当たって疲れて…。
この気持ちを誰にどう持っていけばいいかもわからないのです。
子どもの不安を和らげ、喜ばれる行動4選

自分たちのころとは事情も違う、でも、何とか手助けしてやりたい親心。
では、就活の不安の中にいる子どもにしてあげられることは何でしょうか。
- 理解しようとして聴く
- 人生の先輩としてアドバイスする
- お金や生活面の現実的サポート
- 客観的な情報収集
①理解しようとして聴く
大前提は、親の価値観を押し付けず、子どもを肯定する立ち位置を取ることです。
じゃあ、どうするかというと、子どもを理解しようとしながら「聴く」です。
子育ての間は、親は良かれと思って子どもが歩む道を作ってきたと思います。
しかし、親が作った道は親の「こうしたら良い」で作られています。
子どもは育って、もう自分で道を拓き、歩けるようになりました。
子どもには子どもの価値観があり、親と同じではありません。
親の考えていることと子どもが考えていることは違うのです。
違うのだから知ろうとする。
これが大切です。
子どもが話し終わるまで口を挟まず、相手を理解しようとしながら「聴く」に徹してみてください。
子どもを理解しようとしながら聴く
②人生の先輩としてアドバイス
例えば、あなたが学校で子どもたちに、自分の体験や願いを話をしてくださいと頼まれたらどうしますか?
おそらく、どう話したら伝わるか考えることでしょう。
子ども目線で筋道を立て、わかりやすくしようとしますよね。
言葉も選びます。
ひょっとしたら、諭すこともあるでしょう。
少なくとも感情的に話すことはありません。
その姿勢は親子の会話とは全く異なります。
人生の先輩としての姿勢だと思うのです。
親は、親であるとともに一個の人間として人生の先輩、社会人の先輩です。
子どもにないものは「人生の経験」です。
就活の子どもに聴く耳があるとしたら親の声ではなく、「人生経験の生の声」なのかもしれませんよ。
人生の先輩としてアドバイスをする
③お金や生活面の現実的サポート
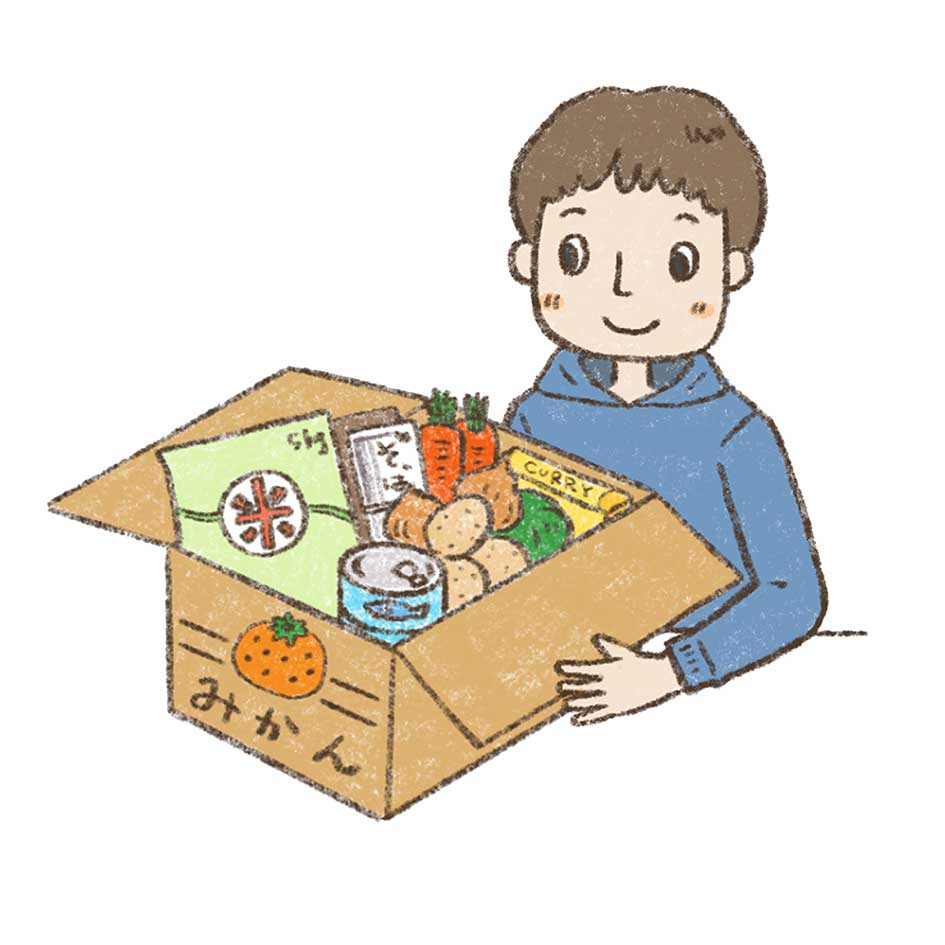
意外かもしれませんが、一番喜ばれるのが金銭的援助と生活面での援助です。
就活にはこまごまとお金がかかります。
スーツ代、交通費、食費など。
アルバイトだけではやりくりが難しい面があります。
現実的にお金の悩みは切実で、そこを援助してもらえるのはとてもありがたいと感じます。
でもでも、出してやったという上から目線はダメです。
そこは忘れずに。
もうひとつは、食事や洗濯、必要な物のサポート。
子どもが遠方住まいなら身の回りのことはできなくても、物質的なサポートはできますよね。
しんどい時の親からの仕送りはホロッとするようです。
お金と生活面の現実的サポート
④客観的な情報収集

インターネットを介する就活は多くの企業にエントリーできるメリットがあります。
反対に、エントリーするための企業研究や分析には時間と労力がかさむデメリットがあります。
そこで、子どもの手が回らないところをサポートすると良いでしょう。
社会情勢であったり、企業情報であったり、今朝のニュースであったり。
頼まれて調べるのが良いですが、そうでないなら、調べたことを会話の中でさりげなく出してみて子どもが興味を持ったら説明するくらいの距離感が良いでしょう。
就活にまつわる客観的な情報取集
ウザい、うるさい親の特徴
親が子どもの気持ちを逆なでし、ウザい、うるさい親になってしまうパターンを考えてみました。
ワースト3です。
- 希望する会社や職種、就職活動に意見する
- 兄弟、親戚、友人などと比較する
- 子どもの気持ちを察しようとしない
思い当たる節はありませんか?
これらは子どもにとっては自分を否定されたり、受け入れてもらえていないと感じる言動になります。
子どもが親に求めているのは、
①自分の置かれた状況や気持ちに共感してもらえ、
②頑張っていることを認めてもらえること。
ここが満たされない時に「ウザい、うるさい親」になってしまいます。
心配であれこれ言ってしまったり、問いただしてみたりするのは親の勝手な都合でしかありません。
子どもにしたら親の勝手な都合を押しつけられているのだから「ウザい、うるさい親」になってしまうのは当たり前です。
親の心配な気持ち、不安な気持ちは親の勝手な都合です。
究極、親ができるのはたったこれだけ
待つ!
待って、ヘルプを求められたら動く!です。
子どもを心配し、親自身不安を抱えていてあれこれ口出しをした結果、ウザい、わかってくれない親になるのです。
「押してダメなら引いてみな」で、逆に距離を取って「待つ」。
放っておくみたいで心配ですか?
心配が心配を呼んで居ても立っても居られない。
黙って待つのがもう無理!
待ってるのがつらい!
こらえ性なく言ってしまうのなら、子どもの居ない所でイライラやモヤモヤを吐き出す方がずっと良いです。
親子関係がこじれるリスクは下がります。
そのために、親がカウンセリングを受けたら良いと私は常々思っています。
親がカウンセリングを受けて自分の心配や不安を吐き出してメンタルが安定すると、子どもを待つことができるし、放っておいても大丈夫と思えます。
子どもを心底信頼できるようになるには、親は親なりに心の整理が必要です。
まとめ
大学生の約9割が不安を抱えながら就活を行っています。
親は親の考えや心配で口を出してしまいがちです。
子どもに喜ばれる親の行動4つは
- 理解しようとして聴く
- 人生の先輩としてアドバイス
- お金や生活面での現実的サポート
- 客観的な情報収集
究極の親の立ち位置は「待つ」
できない時はカウンセリングを受けて、親のメンタルを安定化させるのがお勧めです。
お子さんの就活の成功をお祈りします!