- 健康法で水を飲む意味
- 朝イチに飲む白湯のはたらき
- 白湯の作り方と飲み方
白湯を飲む健康法がブームになったことがあります。
起源はアーユルヴェーダといわれています。
古代医学の世界でも東西を問わず、水と健康の関係は重要なテーマとなっています。
この記事では、朝一番に白湯を飲むことが体にはたらくのかにフォーカスして水と健康の関係を考えてみました。
健康法で水を飲む意味
水は生きていく上では必要不可欠です。
体の中で起きている生理反応は水がなくては成り立ちません。
体は水でできている⁉

人の体の約60%は「水」で満たされているといわれます。
成人男性、体重60kgの人なら36kgが「水」という計算になります。
2リットルの大きなペットボトルで18本。
ひと箱6本入りだと3箱になります。
これだけの「水」が体内をめぐり、細胞を出入りしているのです。
私たちが活動するためのエネルギーを生み出す代謝は「水」がなければできません。
体の構成成分としての「水」をよりよい状態に保つことは健康にとってとても重要なのです。
だから水に注目した健康法が多いのかもしれません。
古代医学では水は重要
水が健康に重要なのは伝統医学をみてもわかります。
白湯を飲む健康法はインドの伝統医学アーユルヴェーダが起源とされています。
インド以外にも中国や韓国、日本でも水は重視されています。
例えば、漢方のバイブル「傷寒論」では、薬を煎じるための水はどういうものがよいかを定めています。
また、西洋でも古代ギリシアの医聖ヒポクラテスは「空気・水・場所」の環境が人間の健康と病気に影響を及ぼすと考えました。
飲む前に知ってほしい「水毒」という考え

漢方では水毒という考え方があります。
体の中を「水(すい)」が巡っていると考えます。
口から入れた水は体の中を巡り、汗や尿、あるいは大便の水分として体の外に排出されます。
健康であれば淀みなく「水」が巡っているのですが、バランスが崩れると「水」を巡らせることができず、体の中で「水」が偏在した状態が生まれます。
「水」が体の中に偏在すると、むくみや、夏場の体の冷え、疲れやすい、花粉症などを引き起こします。
これが水毒です。
偏在している「水」をたくさんの水を飲むことで流し去ろうとするのが1日2リットルの水飲み療法です。
けれど、水毒がある方が急に水をたくさん飲み出すとかえって健康を害します。
心臓や腎臓に負担をかけてしまうのです。
なかなか悩ましいところです。
水毒がある方が無理をして水を飲むのは厳禁です。
 柴田ともみ
柴田ともみ数年前の私は、水が飲めなくて、白湯を飲む健康法や1日2リットル飲む水飲み療法といわれる健康法は体に合いませんでした。
夜寝る前にひとくち水を飲んだだけで、翌朝はむくんでしまうからです。
無理せずにできる範囲でを心掛けて、今は段々飲めるようになっています。
朝一番の体に白湯はなぜ良いの?
白湯を飲む健康法の効果として次の6つがネット上で見受けられます。
- 冷え性の改善
- 血液循環を良くする
- 老廃物や毒素の排出(デトックス)
- 便秘解消
- 美肌
- ダイエット
- 花粉症の改善
次に朝一番に白湯が良い理由を2つあげます。
朝は胃が空っぽ、断食明け
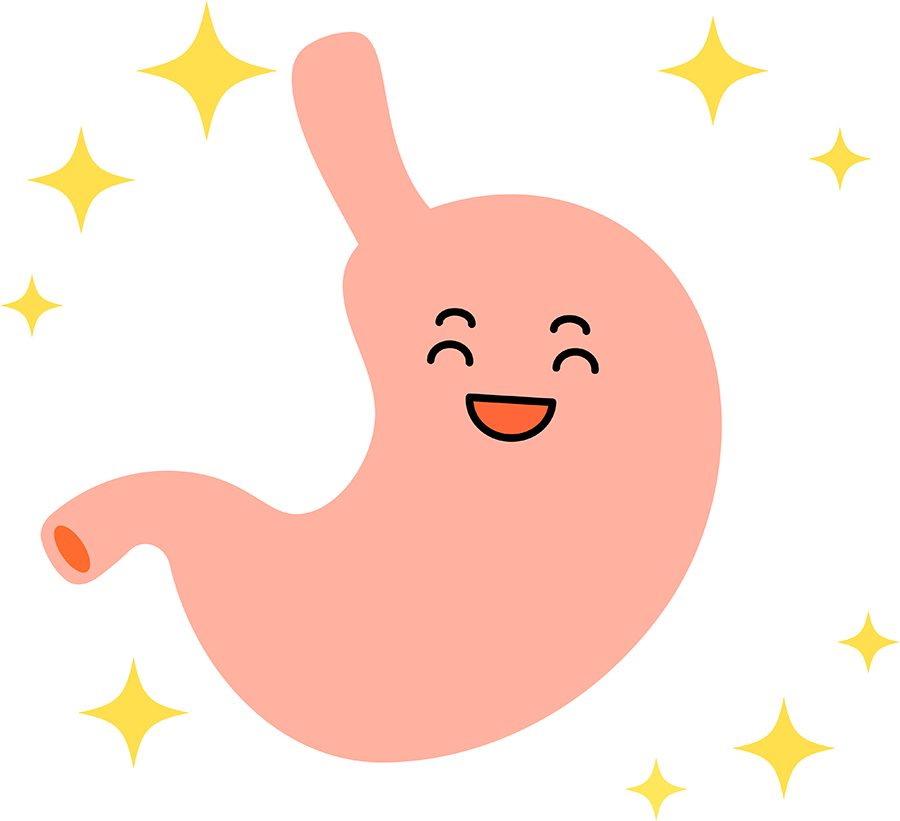
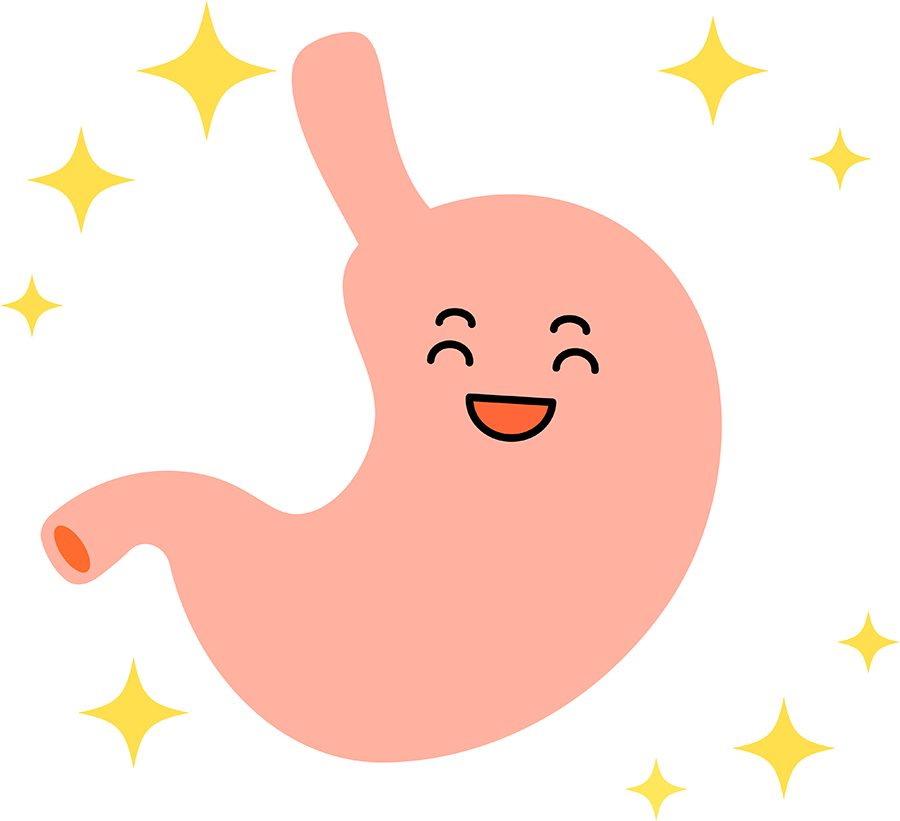
朝一番の白湯は毎日のプチ断食から体を起こしてくれます。
朝食のことをブレックファーストbreakfastといいます。
breakは破る、fastは断食という意味です。
つまり、breakfastで「断食を破る」という意味になります。
多くの人にとって、胃に食べ物が入らない時間がいちばん長いのは前日の夕食から翌日の朝食まで。
この時間は断食状態で、それを破るからbreakfastなのですね。
私たちは毎日プチ断食を繰り返しているようなものです。
眠っている時間は、食べ物だけでなく水も体に入ってきません。
胃は休まっていますが、水を飲まないこの時間は「水」が失われていく時間になります。
眠っている間でも尿や汗が作られるのに口から水は供給されないので、体全体としては渇してしまうのです。
朝一番の白湯は、眠っている間に水分不足になった体や胃腸を優しく速やかに潤し、体を起こしてくれます。
朝は体温が最も低い
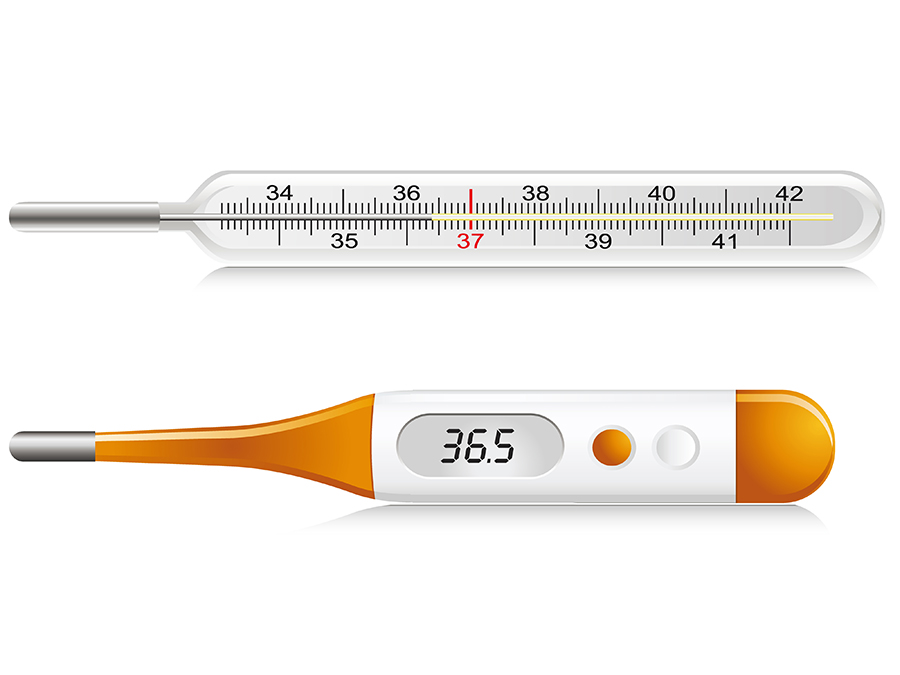
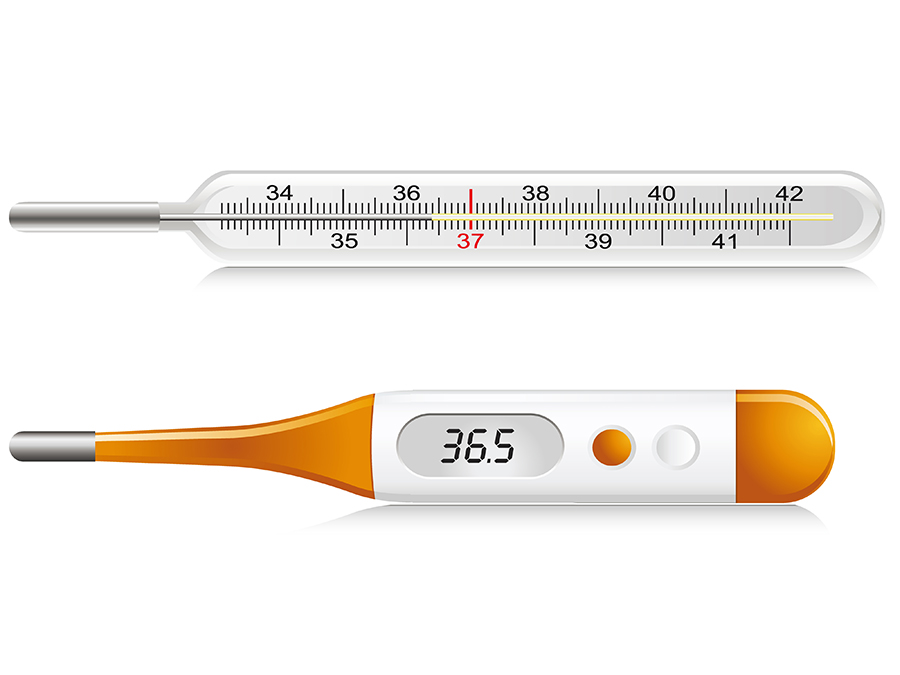
朝一番の白湯は、体を内側から温め、胃を活発にしてくれます。
夜眠っている間、体は生命を維持するのに必要最小限の活動は行っています。
最小限で生きているという感じです。
そのため、体温は一日のうちで朝が一番低くなります。
基礎体温といわれるもので、女性の方は測ったことがある方もいらっしゃるでしょう。
目が覚めてからは、日中の活動によって体温は徐々に高くなり、夕方から夜にかけて最も高くなります。
朝一番に白湯を飲むことは、体が活動し出すきっかけとなります。
体が目覚める感じですね。
特に、胃はわかりやすいです。
※摂取する水の温度と量が朝の胃運動に及ぼす影響が研究されていて、高い温度の水を飲むと、胃の動きが活発になることがわかっています。
65℃で150mL以上の湯は飲水後の胃運動正常波の出現頻度を増加させること、および胃運動正常波の強さは本研究で水の温度と量にかかわらず一過性に増大することが示唆された。
脇坂しおり他「摂取する水の温度と量がヒトの胃運動に及ぼす影響」日本栄養・食糧学会誌 第64巻 第1号 p19-25(2011年)
起き抜けに朝食が食べられない方は試してもいいかもしれませんね。



私は、朝一番に白湯を飲むと、体が温かくなり、お腹がキュルッと動いて朝食を食べたくなります。
胃が動き出すとご飯も美味しいし、排便もスムーズになるようです。
白湯の作り方と飲み方
日本でも「おばあちゃんの知恵」のように白湯は飲まれていました。
風邪を引いたらお薬を白湯で飲んだり、赤ちゃんの離乳食の一番最初はひとさじの白湯から始めるのをご存知な方も多いでしょう。
次に白湯の作り方と飲み方について紹介します。
作り方
アーユルヴェーダの白湯の作り方は次の通りです。
※アーユルヴェーダ独特の考えでは、沸騰させ続ける時、換気扇を回し、風の要素を加えます。
アーユルヴェーダの作り方は時間もかかって忙しい朝には無理!という方は、レンジや湯沸かしポットを利用してみましょう。
飲み方
熱いのをすすりながらゆっくり飲むのが良いそうです。
胃に入るころには温度が下がります。
胃を温めた水が小腸へいく頃には白湯の温度はさらに下がり、吸収しやすい温度になっていると考えられます。
白湯はじんわりと吸収されて胃腸を温め、整えてくれます。
忙しい朝。
ゆっくり飲めないなら、ぬるめで飲みやすい温度、人肌でも構いません。
飲みやすさ、習慣のしやすさを優先しましょう。
量もひとくちから始めて飲める量に納めましょう。
健康法には正解はありません。
その日その時の体調で加減していきましょう。
気楽に続けるのがコツです。



私も、ひとくちしか飲まない時もあるし、コップ一杯を飲む時もあるし、と様々です。
まとめ


水は体にとって欠かすことのできないものです。
朝一番に飲む白湯は体を温め、胃の動きを活発にするので一日のスタートにお勧めです。
水毒という考えもあるので、無理のない量を飲んでください。。
継続は力なり。
「毎日絶対飲まなくっちゃ」ではなく、忘れても「また始めればいいわ」くらいの気軽さが続けるコツです。










