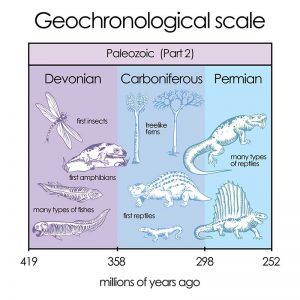- 銀杏の読み方は3つある
- 中医学の薬にも使われる銀杏
- 大人も子どもも要注意なギンナン中毒
- 症状がある場合はすぐに医療機関受診する
秋の味覚に「銀杏」があります。
茶碗蒸しや飛竜頭(がんもどき、ひろうす)の中の黄色いひと粒が嬉しい人もいらっしゃると思います。
炒った銀杏が升に盛られて露店で売られていることもありますね。
好きな人なら次から次へと手が伸びることでしょう。
20個くらいペロリかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
ある映画を観ていて、登場人物の死は銀杏中毒!?と思ったのがきっかけで調べてみてました。
銀杏は少量でも中毒死することがあるそうです。
食べる前にこの記事を読んで注意していただければと思います。
読み方で意味が異なる「銀杏」
漢字では「銀杏」と書きますが、何を指すかによって読み方が違います。
樹木を指す場合はイチョウ、種子としてはギンナン、生薬としてはギンキョウと読みます。
銀杏(イチョウ)は樹木を指す

イチョウは雌雄異株の植物で、その仲間が一億5000万年前にもこの地球に生息しており、今では生きた化石といわれています。
中国原産といわれています。
あのおなじみの葉っぱの形は、私たちがよく見ている木の葉と違い、鴨やアヒルの足に似ているので鴨掌(おうしょう)樹ともいいます。
銀杏(イチョウ)は街路樹でよく目にします。
大阪に住んでいる方ならイチョウと言えば御堂筋の並木が頭に浮かぶのではないでしょうか。
皆さんはいかがですか。
また、古木では、青森県深浦町に樹齢1000年以上といわれる木があります。
化石も見つかっていることから日本には古くからあったようです。
中国の古典には銀杏(イチョウ)は11世紀から登場していて、日本にはそれ以降伝わったという説もあります。
銀杏(ギンナン)は種子を指す
種子は発芽して生長すれば一個の植物となります。
種子は、その小さな一粒で植物一個を作り出す生命力を持っています。
そのため、栄養価も高く精が強いものです。
また、毒を持っているものもあります。
毒を持つのは、鳥や動物に食べられずに芽吹く智慧でもあります。
 柴田ともみ
柴田ともみ例えば、梅干しの種。
種を割って出てくる白い部分、これは仁(じん)といいます。
ここには青酸配糖体アミグダリンという毒が含まれていて、未熟な青梅では濃度が高いため「青梅を生で食べるな」というおばあちゃんの知恵が有名です。
私たちが食べる銀杏も仁の部分です。
銀杏(ギンキョウ)は生薬を指す
毒は、裏を返せば生理作用が強い成分です。
これをうまく使えば薬となります。
銀杏(ギンキョウ)には、肺気を収れんし、喘咳をおさめ、著しく痰量を減少させる効能があります。
中医学(中国)では銀杏(ギンキョウ)を用いた薬は次の3つがあります。
- 定喘湯(ていぜいとう)
構成生薬は、銀杏、麻黃、蘇子、甘草、款冬花(かんとうか)、杏仁、桑白皮、黃芩、半夏 - 鴨掌散(おうしょうさん)
構成生薬は、銀杏、麻黄、甘草 - 易黄湯(いおうとう)
構成生薬は銀杏、芡実(けんじつ)、山薬、黄柏、車前子(しゃぜんし)
日本の医学古典である平安時代の医心方(いしんほう)や、江戸時代の薬性能毒(やくしょうのうどく)には銀杏の記載はありません。
銀杏(ギンキョウ)を使った薬は、日本での汎用性はなかったと考えられます。
ギンナン中毒について
ギンナン中毒死疑惑の映画


2017年に映画「家族はつらいよ2」が公開されました。
【監督】山田洋次(「男はつらいよ」「釣りバカ日誌」各シリーズ)
【配給】松竹
【時間】113分
【原作】「家族はつらいよ2」ノベライズ版
この映画のあるシーンが問題の疑惑です。
周造はドライブ中に偶然、旧友の丸田と出会う。
家族はつらいよ(Wikipedia)
かつて呉服屋の息子で女子生徒からもモテていた丸田であったが、70歳を超えた今、彼は工事現場で棒ふりをしながら生活費を稼ぎ、ボロボロのアパートで孤独に暮らしていた。
丸田を哀れに思った周造は旧友を集め、丸田を励ます会を開く。
久しぶりに美味い酒を飲み上機嫌に酔っぱらった丸田は、周造に連れられて平田家に泊まることになったのだが、朝目が覚めると大変な事態になっていた。
このシーンで、お皿にギンナンの殻が山盛りになっていました。
10個20個どころではない数です。
この多量のギンナンを見て、中毒死を疑ったのです。
ちなみに、ギンナン好きの丸田さんのために棺桶にギンナンをいっぱい入れてあげ、火葬の時にギンナンが爆竹のように爆ぜるのが映画の落ちでした。
ギンナンは何個まで食べられる?


ギンナン中毒について日本中毒情報センターの保健師・薬剤師・看護師向け中毒情報ファイルからまとめてみました。
中毒を起こす量に非常に幅があるため致死量を決められないようです。
毎年のようにギンナン中毒への注意喚起が行われるくらい相談件数が多いようです。
食べる時は大人も子どもも注意してください。
- 経口中毒量は、小児 7~150個、成人 40~300個
- 症状は主に嘔吐と痙攣で、痙攣が反復することが多いです。
そのほか:不整脈、顔面蒼白、呼吸困難、呼吸促迫、痙攣、めまい、意識混濁、下肢の麻痺、嘔吐、便秘、発熱 - 食べてから1~12時間で発症し、死亡例があります。
- ギンナンに含まれる有毒成分は熱に安定で、加熱調理しても消えません。
- 6~7個⾷べてけいれんが出現した 5 歳以下の⼩児の事例があります。



日本にはギンナンは年の数より多く食べてはいけないという伝承もあり、昔から食用には注意がされてきました。
経験からくる先人の知恵に耳を傾けたいものです。
その他の情報として、イチョウの実の果肉部分は、素手で触るとアレルギー性皮膚炎を起こす可能性成分(ビロボールやギンコール酸など)が含まれています。
種子である銀杏(ギンナン)にはビタミンB6を阻害する4-O-メチルピリドキシンが含まれています。
健康食品イチョウ葉エキスは安全?
近年、イチョウ葉エキスが広まっています。
ドイツなどでは認知機能等の改善効果を期待した医薬品として利用されています。
日本ではイチョウ葉エキスを含む健康食品が販売されています。
イチョウの葉には、果肉と同様にギンコール酸が多く含まれています。
ギンコール酸はアレルギーを引き起こす有害物質として知られています。
健康食品は医薬品ほどの成分の厳密さはありません。
有害物質をどのくらい除去できているかは健康食品によって様々で実態がわかりません。



イチョウ葉エキスの健康食品を摂取する場合は、摂取目安量を守りましょう。
イチョウ葉エキスについての詳しく知りたい方ははこちらを参考にしてください。


中毒症状はすぐに医療機関を受診する
食材として銀杏(ギンナン)
栄養
栄養学的には、たんぱく質、カリウム、ビタミンE、ビタミンC、鉄、β-カロテンが含まれています。
選び方
旬は秋。
殻が白くてツヤがあって、大粒のものを選びます。
食べる時の注意点
生食を避けて、火を通してください。
中毒の危険性があるのでたくさん食べないようにしましょう。
薬膳の効能
薬膳食材としての銀杏(ギンナン)は、肺を潤すので、空気の乾燥する秋から冬に取りたい食材です。
咳や痰、慢性的な喘息や気管支炎、頻尿や尿失禁などの不調を整える食材といわれています。
ちょっと専門的になりますが、銀杏(ギンナン)の性質は次のようになります。
まとめ
映画「家族はつらいよ2」を観たことがきっかけで銀杏についてまとめてみました。
生薬としても食材としても銀杏には効能があり古来から用いられてきました。
ただし、ギンナン中毒には気をつけなければいけません。
①経口中毒量は、小児 7~15個、成人 40~300個。
②主に嘔吐と痙攣。中毒死の例あり。
③加熱調理しても有毒成分はなくならない。
④中毒症状がみられたら直ちに医療機関を受診すること。
食べる量が経口中毒量に満たなくても、体調によっては中毒になるかもしれません。
お好きな方には残念なことですが、ギンナンを食べる時はくれぐれも慎重に、食べ過ぎないようになさってください。